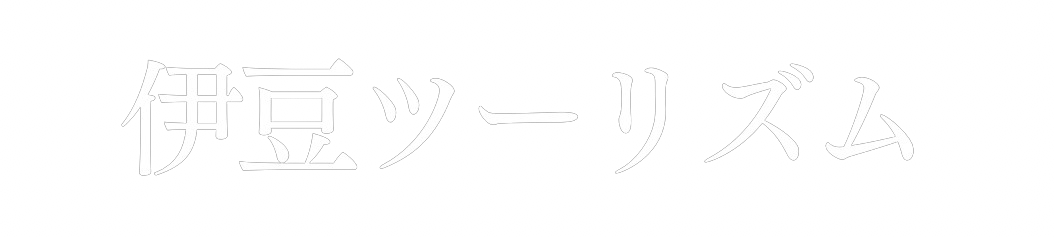スポンサーリンク
目次
修善寺で唯一無二の紙漉きに挑戦しよう
修善寺温泉街から車で約5分の紙谷地区に位置する紙谷和紙工房では、平安時代から約1000年の歴史を誇る伝統的な「修善寺紙」の制作と和紙漉き体験を行っています。修善寺紙は三椏(みつまた)、楮(こうぞ)、雁皮(がんぴ)を原料とし、横縞の透いたすだれ目と薄紅色が特徴の非常に薄く上質な和紙で、源頼朝の決起文や徳川家康にも使用されたと伝えられる歴史ある工芸品です。
体験では単なる紙漉きにとどまらず、修善寺紙の歴史や和紙作りの工程をスライドを使って丁寧に解説してくれます。工房見学では、もと鶏小屋を改装した趣のある建物内で、かまどや湧き水など普段見ることのできない伝統的な道具や設備を間近で観察できます。さらに原材料となるミツマタやコウゾの畑へのツアーも含まれ、桂川のせせらぎや山間の田園風景の中で、都会の喧騒を忘れられる非日常体験が楽しめます。
体験で作ったはがき5枚セット、名刺24枚、美濃版紙1枚から選べる和紙は、草花での装飾も可能で、約1週間の乾燥後に郵送で届けられます。明治末期に一度途絶えた修善寺紙を、令和の時代に復活させた工房の熱い想いと職人技に触れることで、日本の伝統工芸の奥深さを体感できる貴重な文化体験スポットです。
基本情報
| 料金 |
| 和紙漉き体験:5,000円 |
| 住所 |
| 静岡県伊豆市修善寺1302-4 |
| 電話番号 |
| 050-3699-4284 |
| 営業時間 |
| 9:00〜17:00 |
| 定休日 |
| 不定休 |
| 交通アクセス |
| 電車:伊豆箱根鉄道「修善寺駅」からバスで約15分、「湯舟口」バス停下車、徒歩約1分 車:修善寺駅より8分 |
| 駐車場 |
| あり |
| 公式サイト |
| 修善寺紙紙谷和紙工房 |