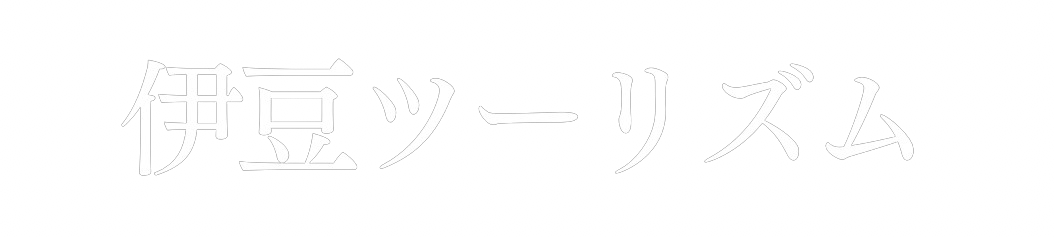スポンサーリンク
目次
怪僧・文覚が草庵を結んだ霊場
毘沙門堂は、国清寺から山道を約1km登った奈古谷の山中に鎮座する古堂です。源頼朝に挙兵を促した怪僧・文覚上人が流刑となり草庵を結んでいた場所と伝えられ、平安時代には安養浄土院(奈古谷寺)と呼ばれる寺院がありました。その後、源頼朝と文覚が大改修し「瑞龍山授福寺」と改められ、毘沙門堂はその鎮守とされました。現在は授福寺が廃寺となり、国清寺が管理しています。本尊は平安時代初期に慈覚大師が自ら彫り込んだと伝わる毘沙門天像で、50年に一度の大開帳、25年に一度の中開帳が行われる秘仏です。
参道の仁王門には、静岡県指定文化財の木造金剛力士像が安置されています。鎌倉時代初期の慶派の作で、延徳3年(1319年)に制作されたものと推定され、寺伝では1186年に頼朝が寄進し、運慶・湛慶の作とも伝えられています。仁王門を過ぎた授福寺跡地には、文覚上人が護摩を焚いたとされる「奈古谷七つ石」のひとつ「護摩石」があります。麓からの参道(毘沙門道)には、蛇石・夫婦石・谷響石・弘法石・大日石・護摩石・冠石という七つ石が点在し、梵字や仏像が彫り込まれた中世以来の石造群が今も残っています。
毎年1月3日には奈古谷毘沙門天の例祭が行われ、早朝祈禱には地域の人々が集まって参拝し、僧侶の読経や御詠歌が響きます。境内では地元消防団主催の「開運だるま市」が開催され、大小様々なだるまが並び、普段は静かな境内が参詣者の活気で溢れます。参道を宝探し感覚で登りながら、真言宗の道場であった痕跡を辿る体験は、伊豆長岡の深い歴史と信仰に触れる貴重な機会となるでしょう。
基本情報
| 料金 |
| 無料 |
| 住所 |
| 静岡県伊豆の国市奈古谷 |
| 営業時間 |
| 参拝自由(本尊は秘仏のため通常非公開、50年に一度の大開帳・25年に一度の中開帳時のみ) |
| 定休日 |
| 無休 |
| 交通アクセス |
| 電車:伊豆箱根鉄道「大場駅」からバスで約11分、「畑毛温泉」バス停下車、徒歩約44分 車:伊豆長岡駅より19分 |
| 駐車場 |
| あり |